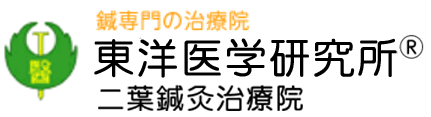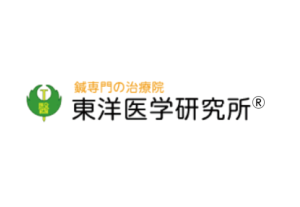研究業績
生体制御療法を使用した鍼治療の研究1・・・健康チェック表とは
1)不定愁訴症候群に対する鍼灸治療の検討 近年、社会構成が複雑多岐になり、現代はストレス社会ともいわれるようになってきました。そして、いわゆる不定愁訴を訴える人が多くなり、これらの人々が鍼灸院を訪れるケースが増加しつつあ […]
局所療法としての鍼治療の研究・・・疼痛疾患に対する鍼治療
鍼治療では生体制御療法と並び局所療法も有効な治療法であります。特に症状に対する局所療法は疼痛疾患(痛みを伴う疾患)に多用されるもので、1回の鍼治療で効果をあげる事ができる場合もあります。現在、臨床で簡便に測定・評価する痛 […]
生体制御療法を使用した鍼治療の研究5・・・未病治に対する鍼治療
鍼治療による「健康・遅老」の健康管理および老化防止と生体防御機構の現象を基礎・臨床にわたり研究しました。 1.基礎研究 マウスの寿命は2~3年といわれており、月齢とともに組織・器官に老化による変化が現れることが知られてい […]
生体制御療法を使用した鍼治療の研究4・・・高血圧に対する鍼治療
高血圧に対する鍼治療として足三里穴を使用する頻度が多い。そこでこの足三里穴刺鍼の血圧に及ぼす影響を臨床的に研究しました。 平成9年6月21日から平成10年8月30日までを募集期間とし、この期間中に最低8回以上鍼治療を行 […]
生体制御療法を使用した鍼治療の研究3・・・糖尿病に対する鍼治療
今日の糖尿病治療の目的は一次予防(糖尿病の発症を予防する)と二次予防(糖尿病の合併症を予防する)および三次予防(合併症を管理して、重篤な臓器傷害の状態または死に至らないよう予防する)であります。 糖尿病治療は食事療法や運 […]
生体制御療法を使用した鍼治療の研究2・・・慢性肝機能障害に対する鍼治療
1)基礎研究 ①実験的肝傷害に対する鍼の効果についての超微形態学的研究 四塩化炭素を投与した肝傷害モデルマウスと鍼治療を施したマウスにおける肝臓の超微形態を比較観察しました。 肝傷害マウスでは、肝細胞核内に偽核封入体 […]
生体制御療法を使用した鍼治療の研究1・・・不定愁訴症候群に対する鍼治療
N大学病院心療内科で1年以上症状が固定している患者に対し、生体制御療法を目的とした鍼治療を行い、健康チェック表の評価基準を使用して評価しました。鍼治療は生体制御療法(黒野式全身調整基本穴)を使用し、1クールを7回として3 […]
超音波と鍼の併用治療・・・超音波を使用することの意義は?
東洋医学研究所ョでは鍼治療と超音波治療の併用による鎮痛作用の有効性を研究し、その結果を定量的に見出す目的で東洋医学研究所に来院した1649名に医師の診断結果後、治療を施しました。 超音波(US)治療器は伊藤超短波社製US […]
生体制御療法としての黒野式全身調整基本穴・・・使用経穴は如何にして決められたか?
昭和31年から昭和43年までの13年間に、東洋医学研究所®に来院した患者中、近代医学の診断結果を得た、内科領域で同一主訴を5例以上有する患者2083名を対象としました。 最初の患者に対する選穴は、経験的に得た経穴を適宜選 […]